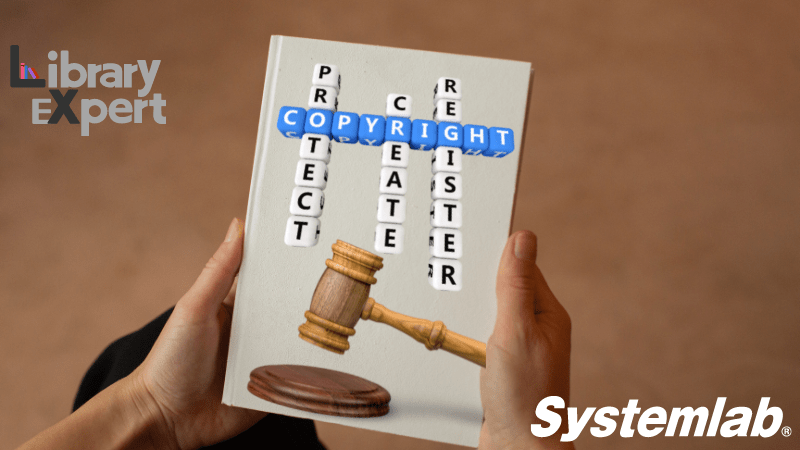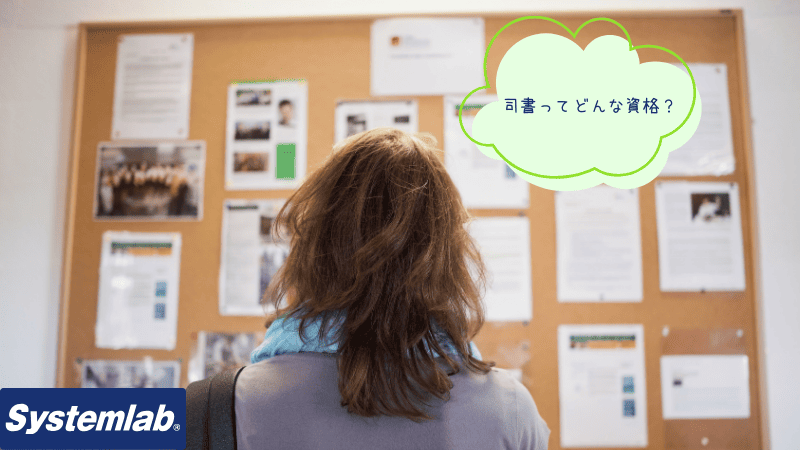
職場に図書室を設置することになったら、誰かしら担当者を置く必要があります。専任者を新規に採用するのか、それとも事業所内から適任者を選ぶのか、悩ましい選択になるかもしれません。もし図書室担当を命じられたら、司書資格は必須なのでしょうか。
司書資格を取得するには
司書は図書館法に定められている国家資格です。
- 大学・短大で司書養成科目を履修
- 大学などが開講する司書講習を受講
等の方法で取得でき、毎年およそ1万人程度が資格を得ています。医師や弁護士のように、全国統一の国家試験はありません。
参考サイト
ただし、そもそも図書館法自体が「一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設」、つまり公共の図書館を前提とした法律のため、その履修内容は、特に私企業にとっては一見「関係なさそう」に見えるものもあります。
- 「図書館に関する法律、関連する領域の法律、図書館政策について解説するとともに、図書館経営の考え方、職員や施設等の経営資源、サービス計画、予算の確保、調査と評価、管理形態等について解説する」(「図書館制度・行政論」)
- 「生涯学習及び社会教育の本質と意義の理解を図り、教育に関する法律・自治体行財政・施策、学校教育・家庭教育等との関連、並びに社会教育施設、専門的職員の役割、学習活動への支援等の基本を解説する」(「生涯学習概論」)
- 司書資格取得のために大学において履修すべき図書館に関する科目の在り方について(報告)
などの内容は、「公務員になるわけじゃあるまいし」と感じるかもしれません。
もちろん学ぶのはこれだけではなく、図書館の意義、図書館にはどんな資料があってそれぞれどのような特性があるか、どのように選べばよいか、資料を有効に提供するための処理(分類やデータ作成)、著作権、レファレンスサービス(利用者対応)等々、必要な知識を得るための科目が並んでいます。
「免許」ではなく「資格」
ただし、資料の分類や書誌(資料に関する記録)作成、情報検索等、実作業につながる科目も、基本的には座学です。分類の問題のうち正解率〇パーセント以上、レファレンス(利用者からの質問)回答を制限時間以内に正答率△パーセント以上、などの到達度を測る統一基準は設けられていません。また、実施している機関もありますが、教員や学芸員、医療・看護のように、一定期間現場に入って行う実習が必修ではないため、司書資格はオンラインの講習や通信教育でも取得が可能です。
参考サイト
資格を持たずに図書館・図書室に配属され、業務上必要になって取得した、というケースも多いようです。司書は資格であって免許ではないので、「司書でなければ図書館(図書室)で働いてはいけない」という規則は存在していないのです。
実際、図書室の規模によりますが、実務をこなすのに資格取得が「必須」とまでは言えないかもしれません。必要な資料については、まず社内で本やデータベースに詳しい人にヒアリングする、ネット検索すれば他の図書館の分類方法はいろいろ調べられますし、図書館システムを外部に依頼している場合は、その担当者に相談することもできるでしょう。情報を入手する方法はいくらでもありますし、独学でも、日常業務に困らない程度習熟することは可能だと思います。
新規採用?人事異動?図書室を誰に任せるべき?
一般の企業で図書室(資料室)を新設することになった場合、どんな人材を置くべきでしょうか。採用するなら、司書資格を持っていて同業もしく近い業種の図書室でキャリアを積んでいる人が望ましいですが、選択範囲はかなり狭くなるでしょう。司書有資格者を条件に求人を出せば、「本が好き」「図書館で働きたい」人の応募が相当あると思いますが、その企業の業務分野にどれほどの知識・熱意があるかは未知数です。また、企業等の図書室では、資料の購入、予算の管理等、さまざまな社内の折衝を少ない担当者が一手に担うことになります。図書館での勤務経験はあっても、ある程度、上の立場で仕事をしていなければ、そういった実務には慣れていないかもしれません。
社内で司書資格を取得している人材が見つかったら、好都合のように思えます。でも、その人材は図書室勤務を希望しているでしょうか。残念ながら、世の中には図書室(資料室)担当といえば「閑職」「ラクな仕事」というイメージを持つ人もいます。企業の業績が良いときに脚光を浴びるのは製品開発や営業担当者等の「稼ぐ人」なので、図書室(資料室)への異動を「キャリアアップの道から外れてしまった」と感じてしまうかもしれません。また、図書室は一人もしくは少人数のスタッフで回していることが多いため「休みが取りにくそう」と敬遠される可能性もあります。
図書室担当者に必要な要素は、単純なことですが「やる気」と「向き・不向き」です。
たとえば、司書を目指す動機が「数字で測られるような仕事はしたくない」「静かな職場で働きたい」「人と接するのが得意ではない」といった人の場合、少人数のスタッフですべてをこなさなければならない図書室には不向きかもしれません。図書室の予算の獲得には利用実績をアピールしなければなりませんし、面倒な質問をしてくる利用者を「それは図書室にありません」と追い返すこともできません。スペースも予算も限られた図書室の場合、必要な資料はどこで入手できるか、頭も足も駆使して探すことが仕事です。また、たとえ社会的な評価の高い資料でも、それが自社の図書室には必要なのかどうかは、社内の動向に疎いようでは判断できないでしょう。
逆に、ニュースにはマメに目を通して新分野の動向に目を光らせ、勉強会等へ積極的に参加する、そんな意欲的な人にも、図書室では日々必要な作業が待っています。資料に向き合い分類記号を考え、返却された書籍を書架に戻し、ときには、古い資料のデータ入力に何日もかかりきりになったり、廃棄する本を箱詰めするだけで一日が終わってしまうこともあります。一連の作業を「地味な仕事でつまらなそう」と感じる人にお勧めできる職業でもないのです。
とはいえ、コミュニケーション能力が高く専門知識に富み、司書資格を持っていて地道な作業を精密にこなす、幻のような人材を探し回っていてもキリがありません。必要な折衝は上司・所属部署で協力して行う、研修や勉強会等への積極的な参加を促し各種のプロジェクトに図書室スタッフを加える、細かな作業が大量に発生するときには外注も考慮する、など、図書室が孤立した存在にならないよう、育成・サポートしていくことが重要です。
司書は宿題の答えを教えてはいけない?
公共図書館は、夏休みに入ると子どもむけに「自由研究のヒント」「読書感想文の書き方」etc.「宿題対策」の本を並べますが、司書資格の勉強では「(司書は)宿題の答えを教えてはいけない」と教えられます。「夏休みの日記を溜めちゃった!」という子どもに対し、司書の役割は「このサイトが参考になるかも」という情報を提示するところまでです。
参考サイト
それでも「図書館とは」をつねに考える
図書室の担当スタッフには「司書資格が必須とはいえない」面ばかり強調してしまいましたが、最後に、司書採用試験にも出題されることがあるという、S.R.ランガナタン(インドの図書館学者 1892-1972)の『図書館学の五法則』をご紹介します。
健康問題や法律相談など、公の図書館勤務を前提とした司書の勉強では「直接回答してはいけない質問」にはどんなものがあるか、なぜ答えてはいけないのか、を図書館の目的や意義とともに学びます。もちろんそれは大切なことなのですが、企業等の図書室に「どこまでやるか」の制約はありません。一つの質問に対して異なる見解が見つかった場合、図書館の司書はそれぞれの資料を提示しますが、企業等のスタッフはそれに加えて「どちらが正しい(と考える)か」の判断を求められるかもしれません。また、どうしても見つからない資料があった場合、単に見つからないのか、それともそもそもそんな資料は存在しないのか(どこかに間違いがあるのではないか)、追及するのも仕事のうちですし、その過程では、公開情報を検索するだけでなく、各方面へ問い合わせたり、直接出向くこともあります。司書は「仮定または将来の予想に属する問題」には回答できませんし、主観の入った「~だと思います」という回答はNGですが、図書室のスタッフには「最近の研究で先鋭的な内容の本」「できるだけ権威のありそうな資料はどれ?」「内容をざっくりまとめて教えて」といった、知識量と判断力が問われる質問にも答えるだけのストックが必要とされます。どんな仕事でも言えることですが、それは何か1冊の本を読めば身につくものでもなく、日々の実務と経験から積み上げていくものです。単純に資格の有無だけで判断できるものではありません。
- 第一法則:Books are for use.(図書は利用するためのものである。)
- 第二法則:Every reader his or her book.(いずれの人にもすべて,その人の本を。)
- 第三法則:Every book its reader.(いずれの本にもすべて,その読者を。)
- 第四法則:Save the time of the reader.(読者の時間を節約せよ。)
- 第五法則:A library is a growing organism.(図書館は成長する有機体である。)
100年近く前に発表されたものですが、時代が変わっても、また規模や種別を問わず、すべての図書館・図書室で働く人にとって、指標となる言葉ではないでしょうか。日々の仕事で「図書館(室)ってなんの役に立つんだろう」「そこで自分に何ができるのか」という疑問が浮かんだとき、資格を取得するため学んだことのなかに、その答えが見つかるかもしれません。司書という資格の名称ではなく、資料と利用者を結びつける「専門家」として評価されるために、「図書館(図書室)は誰のためにあるのか」をつねに考え続け、知識や経験を積んでいきましょう。
こちらの記事もお勧め
株式会社システムラボは便利な図書管理システムをより多くのお客様にご利用いただくために誠心誠意、サポートさせていただきます。少しでも気にれなばお気軽にお問い合わせください。
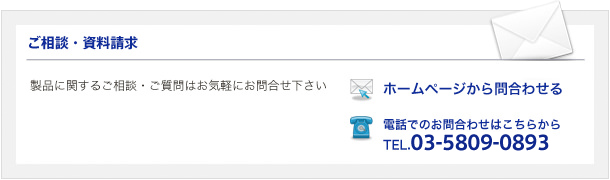
株式会社システムラボ
TEL 03-5809-0893
東京都北区田端6-1-1 田端アスカタワー 12階