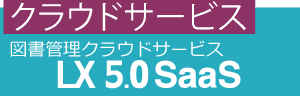本や雑誌を読みたいときに、パソコンやスマートフォンを利用するのは当たり前の時代になりました。図書館(図書室)も例外ではありません。電子書籍(電子ブック)、電子ジャーナル、データベースなどデジタル資料は、デバイスと通信環境さえあればどこからでも利用できるうえに、場所を取らず、必要な情報を素早く検索できます。良いことずくめのようですが、管理する側はどのようなことに留意すればよいのでしょうか。
ハゲタカも狙う高額市場とオープンアクセス(OA)化
図書室の設置目的によっては外国で出版されたものも含め、学術雑誌を収集する必要が生じます。電子ジャーナルを「紙媒体の雑誌をデジタル化したもの」と定義すれば、「スマホで定額読み放題」サービスも含まれますが、「電子化された学術雑誌」にはその権威ゆえ代わりの存在がなく、価格競争が生じません。特に外国の雑誌は、少数の大手商業出版社による寡占状態などの要因により価格の上昇が続き、さらに円安が追い打ちをかけ、大学図書館等の研究機関で大きな問題となっています。
世界の科学出版界の実態 野依良治の視点(21)研究開発戦略センター(CRDS)2017年12月7日
そんな流れに、契約を「分野(や出版社)一括」にして少しはお得になるよう仕向けたり、また、図書館が連合を組んで交渉に臨んだり、と策は講じられてきました。近年では研究成果へは一部の高額購読料を支払える人だけでなく誰もが到達できるようにするべき、という考え方から「オープンアクセス(OA)化」が急速に進みました。たとえば、Google Scholar(グーグル・スカラー Google社の学術論文検索用エンジン)の検索窓に「キーワード(ここでは「トランプ 関税」)」を入れるだけで、2000件以上がヒットしますが、「PDF」と表示されている論文は、すべて無償で公開されているものです。
が、OA化に伴う新たな問題も生じています。「ゴールドOA」と呼ばれるOA化手法では、論文の執筆者が権威ある学術誌に掲載手数料を負担することで無料公開が実現するのですが、この手数料も高騰したり、また、手数料によるもうけを目的とした「ハゲタカジャーナル」(あたかも影響力の強い学術誌であるように装って研究者を勧誘し、粗雑な編集で掲載したうえに高額の費用を要求する電子ジャーナル)まで存在するそうです。それでも、特に公的資金による研究については、世界的に国を挙げて無料公開の義務化が推奨されており、日本でも下記の通り基本方針が定められました。
学術論文等の即時オープンアクセスの実現に向けた基本方針 内閣府 統合イノベーション戦略推進会議決定 2024年2月16日
小規模な図書室では、Webから即時に入手できるOA論文はたいへんありがたい資料です。下記のような検索サイトを活用し、有償の論文は臨機応変に購入を検討するなど、対策を講じるとよいでしょう。
検索サイト
- CiNii Articles
- J-STAGE
- IRDB (学術機関リポジトリデータベース)
- Google Scholar
- DOAJ(Directory of Open Access Journals)
OA論文について「内容は大丈夫なの?」という不安を感じた場合、執筆者や、掲載誌の母体である学会や大学等の信頼度に頼ることになります。掲載元がどのような機関なのか、面倒な作業ですが常に情報収集することも必要です。
参考サイト
ハゲタカジャーナル/出版社/学会に注意 慶応義塾大学メディアセンター
「ウチでも使いたい」と声が上がったら~担当者がやるべきこと~
これまで冊子体で購入していた資料が電子化された、利用者から「〇〇って便利らしいけどウチでは使えないの?」と要望があった、「オトクなキャンペーンやってますよ」と売り込みがあったetc.きっかけはさまざまですが、新たなデジタル資料を導入すべきかどうか、作業はどのように進めたらよいでしょうか。
需要を見極める
まず、管理システム上で統計が取れるようなら、同一分野の雑誌や書籍がどのくらい利用されているか、データを出してみることが考えられます。利用者から希望の声が上がった場合は、なぜ使ってみたいと思うのか、既存の資料では代替が利かないのか、等をヒアリングすることも必要です。この人はデジタル資料に詳しそうだな、と思い当たる利用者には、どんどん意見を聞いてみましょう。
価格は適正か?
需要の多いデジタル資料(法律事務所向けの判例検索データベース等)には、複数の選択肢がありますので、各サービスの内容を、資料の重要性、データの充実度、使いやすさ、価格等の面から比較検討します。ここで注意しなければならないことが、利用条件による価格の違いです。たとえば電子書籍の場合、DVDなどを図書室内のPCで閲覧するのと、同じ内容を1,000人規模の事業所が全員Web上で利用可能にするのでは、費用はひとケタどころかふたケタ違います。要するに、実際にいくらかかるかは、先方に確認しなければ分からないことがほとんどなのです。各サービスの担当者と連絡を取り、利用条件を確認して見積もりを依頼する、比較対象が多ければかなりの作業量になりますが、避けては通れません。もし同業者に相談できれば、具体的な価格は守秘義務を課されていて明かしてもらえないかもしれませんが、「相場観(高いのか安いのか)」を養う材料になるでしょう。
利用条件を検討・確認する
アクセス方法
かつては、閲覧を図書室内のPCに限ることもありましたが、それではデジタル資料の利便性を活かすことができませんので、まず、どのように利用したいのかを考えます。一人一人がID/PWを取得してログインする方法は単純ですが、管理者側にはID/PWを新設・削減する作業が発生し、利用者側には「使おうとしたけど、パスワードを忘れてしまった!」等のトラブルが起こりがちです。組織がネットワーク上の住所であるIPアドレスを取得している場合は、同一IPアドレスからのログインはすべて許可されるため、利用者はいちいちパスワード等を入力する手間が省けて快適です。どちらの方法をとるにしても、利用資格者(ID/PW取得者)の総数や、IP認証では同時にアクセス可能な人数で費用が変動する可能性があります。便利な資料を広く活用してもらいたいのはやまやまですが、予算との兼ね合いで、「誰がどのくらい使えるようにするのか」は慎重に検討する必要があります。
特にIPアクセスの場合、IPアドレスを「引っ越し」する可能性もありますし、リモートワークを実施しているかどうかによっても、利用環境は異なります。社内システム担当者へは尋ねることが多々ありますので、事前によく相談しておきましょう。
参考サイト
バックナンバー、プリントアウト
電子ジャーナルの場合、契約によっては過去分が利用できなかったり、逆に最新号は冊子体のみで収録まで時間がかかることもあります。「さあ、もう紙は不要だ!」と棚をきれいにしたくなりますが、サービス自体が他の会社に移ってさらに高額化→やむを得ず解約、雑誌自体の廃刊、等のトラブルが起きないとは言えません。導入後、冊子体の購入やバックナンバーをどうするかは、資料の重要性によって慎重に見きわめる必要があります。
プリントアウトややダウンロードについても、事前に確認します。すべて不可、というサービスはほぼないと思いますが、印刷はできてもダウンロード禁止のサービスや、印刷総量が制限されたり、費用がかかる場合もあります。
トライアル
冊子体の書籍や雑誌のように現物を手に取って確認することができませんので、デジタル資料では「まずはトライアルしてみませんか!」という売り込みがよく舞い込みます。軽い気持ちで実施したものの、繁忙期と重なってログインがゼロだった、では意味がありません。トライアル期間は1か月程度が多いですが、延長してもらえることもありますので、実施時期や期間については、先方と交渉しながら適切なタイミングを探ります。トライアルでは、事前の周知はもちろん、どのようにフィードバックしてもらうかも重要です。アンケートは広く簡単に意見を集められますが、細かな要望まで拾いきれないかもしれません。特定の利用者へのヒアリング、グループインタビュー等、できる限り「生の声」を収集するよう工夫しましょう。
契約
いざ契約!にあたっては、支払い方法(振り込みかカード決済か、請求書・領収書等の発行方法)、契約書のサインは誰がするのか(社判や代表者印は必要か)、契約書保管の規則等、契約するサービスや所属組織のルールによって異なりますので、先方にはもちろん、組織内の各担当部署とも、事前に詳細な検討が必要です。また解約の手続きも要注意です。いつでも止められる、というサービスより、通告の期日(2か月前等)が定められている方が多いため、サービスを次年度も継続するかどうか、担当者には年間を通じたスケジュール管理が求められます。
外国の資料の場合、このような先方への連絡や契約の諸事を代理店に一括して依頼することもできますが、手数料はかかります。
周知
デジタル資料は、宣伝しなければ誰も目にすることはありませんので、組織内で利用方法を周知する必要があります。概略やログイン方法をまとめた動画・リーフレット等を作成して図書室内やWebサイト上に置いたり、先方に依頼して利用講習会を開催する、といった方法が考えられます。
多くの人に利用してもらうためには、入口を分かりやすくするのが大切です。デジタル資料を一覧できるリンク集の作成がまず考えられますが、図書館システムと連携(デジタル資料名でデータを作成し、リンクをクリックするだけでアクセス可能とする等)できれば、たいへん便利です。LX担当者にご相談いただけましたら、どのような方法が考えられるか、ご一緒に検討させていただきます。
トラブルへの対応
利用者から「つながりません!」と連絡があったとき、どのように対応したらよいでしょうか。
サービス提供側に原因はないか(アクシデントやメンテナンスで止まっている、リンク先の変更等)、まずは組織内の別のPCからアクセスしてみてみます。そこでもトラブルが確認された場合は、先方と連絡を取り合って組織内に周知し、後は待つしかありません。一方、問題なく利用できれば、利用者側(のPC等)になんらかの原因があることが推測されます。単純に、リンク先変更のお知らせを見逃していただけ、ということもありますし、OSやブラウザのバージョンが支障になっているのかもしれません。図書室の担当者だけで解決が難しければ、システム担当者にも相談して、解決を図ります。OSやブラウザが原因のトラブルは多くの利用者に発生する可能性がありますので、対処方法をまとめておくと次の対応がラクになります。
利用状況の確認
デジタル資料では、利用状況もデジタルデータで把握できます(「守秘義務」等を理由に提供されないこともあります)。いつどのくらい利用されているのか、データを定期的に確認することで、サービスの継続、また利用可能なアクセス数を増やす(減らす)かどうか、図書室の費用を考える際の参考資料となります。利用状況のデータには取得期限が設定されているものもありますので(〇か月で消去)、予算検討時に慌てて取得するのではなく、定期的な作業としてスケジュールに入れておくことをおすすめします。
リンク先の確認作業、PC・OS・ブラウザそしてサービスそのもののバージョン変更対応、利用状況の確認、契約の更新と予算折衝等、図書室の担当者にとってデジタル資料は「際限なく手間がかかる」と疲弊した気持ちにさせるものかもしれません。それでもデジタル資料は日々進化し、各種のリサーチに欠かせない存在になりました。先方の担当者でも組織内のエンジニアでも、「なんでも(特にPCや通信環境!)相談できる人」をつかまえて、一人で抱え込まずに、利用者の利便性向上のために力を注ぎましょう。
参考資料
はじめての電子ジャーナル管理 改訂版 JLA図書館実践シリーズ 35 保坂睦著 日本図書館協会
こちらの記事もお勧め
株式会社システムラボは便利な図書管理システムをより多くのお客様にご利用いただくために誠心誠意、サポートさせていただきます。少しでも気にれなばお気軽にお問い合わせください。
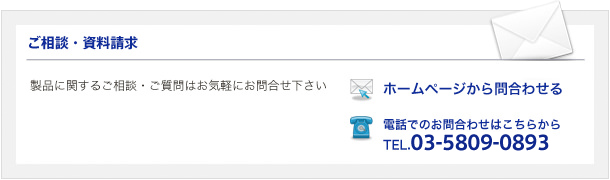
株式会社システムラボ
TEL 03-5809-0893
東京都北区田端6-1-1 田端アスカタワー 12階